幼稚園や小学校低学年くらいの子供は傘の使い方に十分慣れていないことがあります。
いずれは何度も使うことを繰り返すことで自然に身についてくるでしょうが、早く身に着けることができたら助かりますよね。
今回はそんな子どもたちに早く傘の使い方をマスターしてもらえるように、ポイントをまとめてみました。

雨の日 ぬりえ
幼稚園や小学校低学年くらいの子供は傘の使い方に十分慣れていないことがあります。
いずれは何度も使うことを繰り返すことで自然に身についてくるでしょうが、早く身に着けることができたら助かりますよね。
今回はそんな子どもたちに早く傘の使い方をマスターしてもらえるように、ポイントをまとめてみました。

雨の日 ぬりえ

雨の日に登校する前に準備しておきたいこととは?
雨の日に登校・登園する際に気をつけておきたい3つのこと
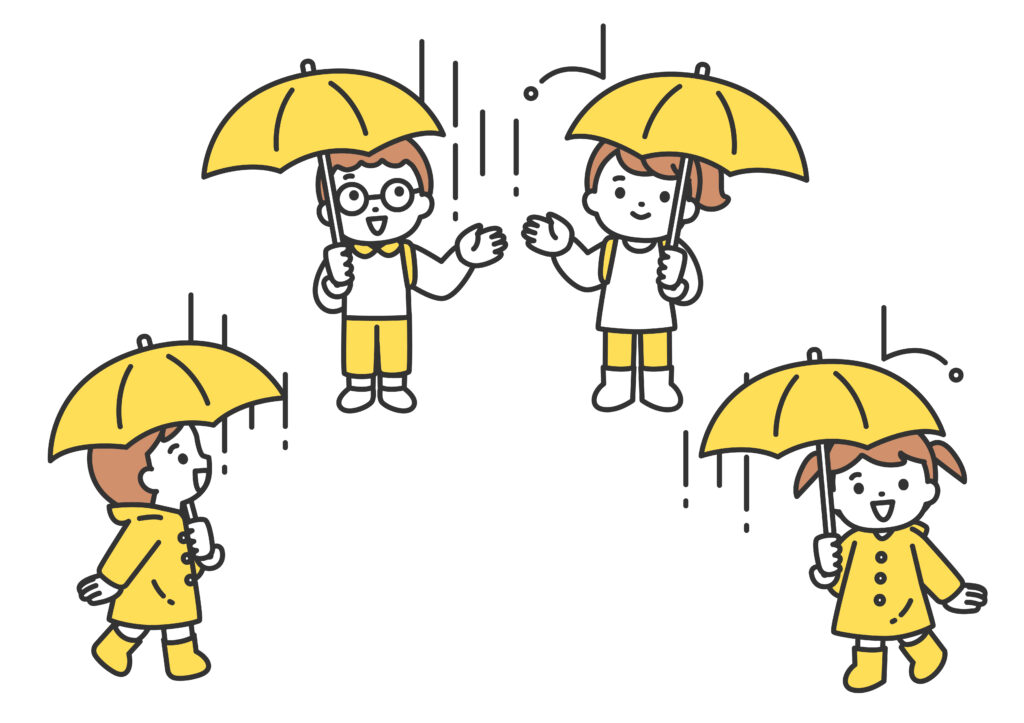
雨の日の登校・登園ルールを子どもといっしょに考えよう



小さな子供は、体格や体力の関係で傘をうまく扱えないことがあります。また、雨が降ったら傘を使うことが結びつかなかったり、傘以外のことに気をとられてしまうこともあります。
そんな子供が安心して傘を使えるようになるためには、事前に準備をすることが大切です。
・傘を選ぶとき、投稿・登園前など事前の準備
・傘の使い方、使っているときの約束
・しまい方、持ち歩くときの約束
などを子供と一緒に確認していきましょう。
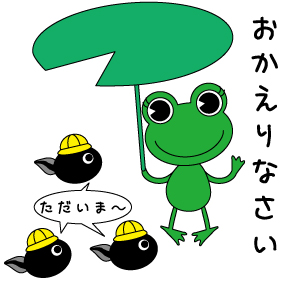
雨の日の散歩は、晴れの日にはない特別な感覚を味わうことができます。
雨の強さによって変わる雨音や、土中のバクテリアによって作り出される雨の日独特のにおい、肌がしっとり湿る感覚などは、実際に外に出ないと感じることはできません。
カタツムリやカエルなどの生き物探しをしてみても面白いでしょう。
また、いろいろな大きさの入れ物を用意して雨粒を受けると大きさによって音の変化を楽しむこともできます。
また普段は禁止されている水たまりで遊ぶことも喜ぶのではないでしょうか。
風呂場で傘を使って水遊びは、水の勢いや流れる感じを体感するとともに、傘の使い方や水の受け止め方などを会得することができます。
また傘の使い方が身についていないときは遊びを通して慣れることができるので役に立つ遊びかも知れないですね。
