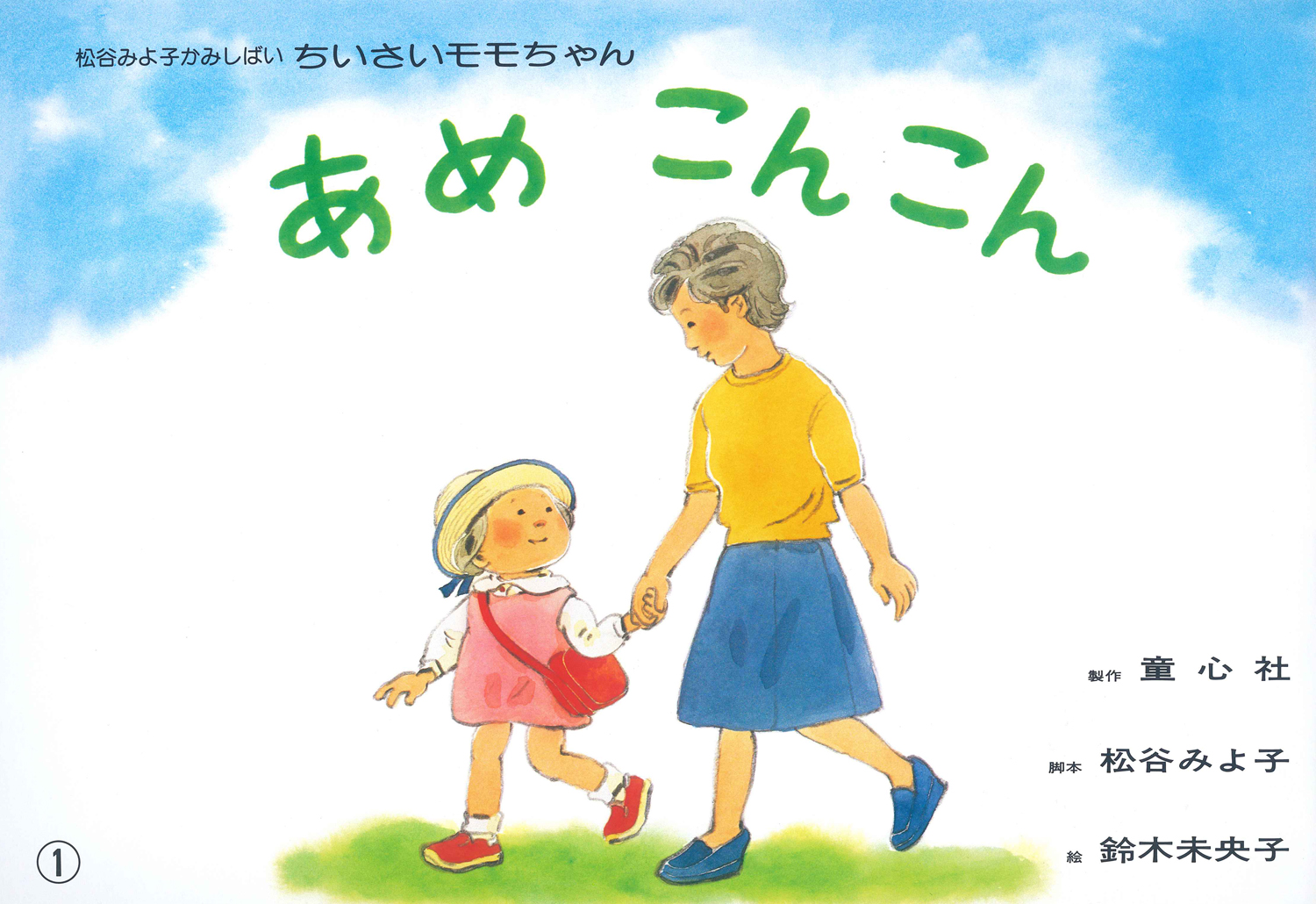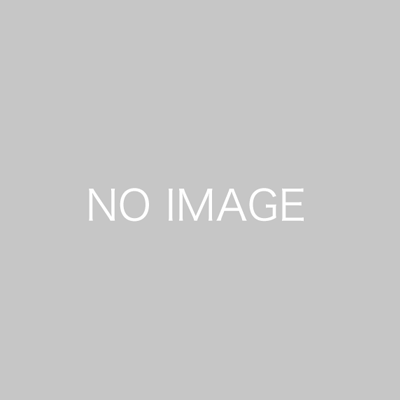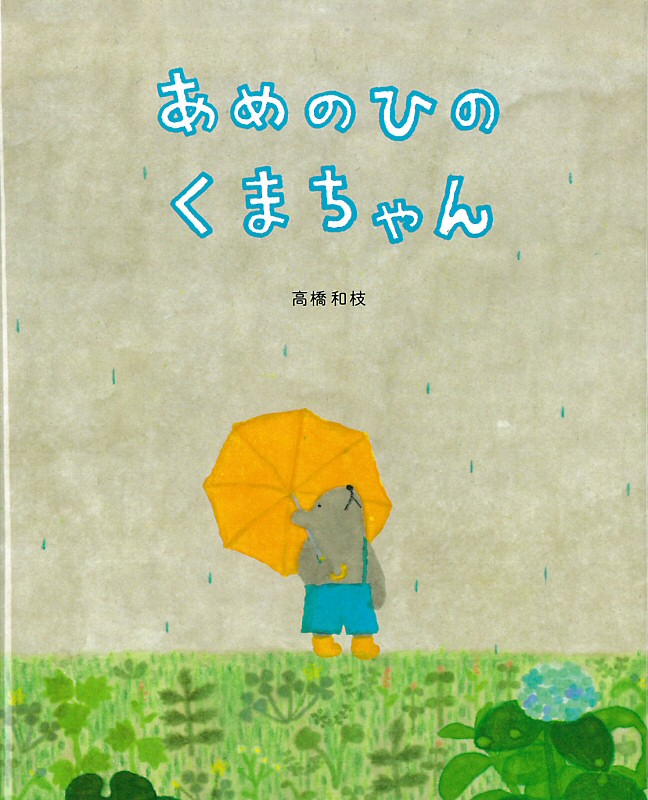傘は日常的な道具でありながら、物語の中では様々な象徴性を持つアイテムとして描かれてきました。
雨から守る実用的な道具としてだけでなく、空を飛ぶ道具、冒険のきっかけ、心の変化を表すシンボルなど、多様な役割を担っています。
本記事では、傘をテーマにした代表的な絵本をいくつか紹介し、その全体的な傾向を考えてみました。
傘と絵本 雨の日に心温まるストーリー
傘をテーマとした絵本の魅力と傾向
代表的な傘をテーマとした絵本
『あめふりさんぽ』(作 えがしらみちこ)
お気に入りのかさもって、ながぐつはいて、カッパ着て、じゅんびできたよ、いってきまーす。
水彩画で描かれるのは、透明感あふれる美しい雨の情景。
女の子と生き物たちの穏やかな雨の日のひとときは、おとぎ話の世界に迷い込んだようです。
どんより天気も楽しくなる絵本。

ちいさいモモちゃん あめこんこん (松谷みよ子 脚本/鈴木未央子 画)
モモちゃんは、かさと長ぐつを買ってもらって大よろこび。
雨がまちきれなくて、庭で雨ふりごっこをはじめました。
あかいかさ(作・絵:ロバート・ブライト 訳:清水 真砂子)
赤いかさを持って出かけた女の子。
動物たちがかさに入れて、と集まってきます。
ウサギもキツネもニワトリも、そして大きなクマまでが……。
かさのなかで楽しいコーラスがはじまります。
まほうのかさ (作:小沢正 絵:はた こうしろう)
運動がとても苦手ないちろう。
いつも大嫌いな『体育』の時間は雨にならないかなあ……と空を見上げて念じていました。
けれど、願った通りにお天気を自由に変えることなどできません。
すると、ある晩、不思議なマントを着た風変わりな女の子と赤い傘の夢を見て……。
ちいさなきいろいかさ (作:もり ひさし 絵:西巻 茅子)
ちいさなかさ!きいろいかさ!ばくさんも、きりんさんもはいったふしぎなかさ!
大好きな黄色のかさを買ってもらって、はじめてひとりで散歩にでかけた女の子の、新鮮な感動をさわやかに描きます。
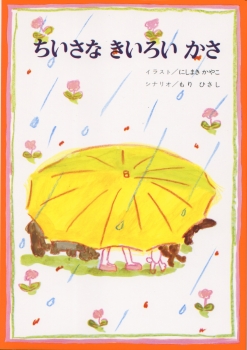
あめあめぱらん (文:木坂 涼 絵:松成 真理子)
あめあめぱらん ぽつぽつぱらん……
うかぶははっぱ はっぱはみどり
みどりはかえる かえるはうたう……
シンプルなことばあそびと、美しいやわらかな水彩画で、子どもと雨のささやかなひとときを描いた絵本です。
あめ ぽぽぽ (作:ひがし なおこ 絵:きうち たつろう)
ある雨の日、ぼくはママといっしょに公園に出かけます。
ぽぽぽ、さあさあ、ぴとぴと、じゃくじゃく、きらきら…など、歌人・東直子がつむぐ、リズミカルに光る言葉の数々。
子どもも大人も心地よくなる、雨粒が語りかけてくる絵本です。
あめのひのくまちゃん (作:高橋 和枝)
雨ってすてきと思える絵本。
さっきまで遊んでいた野原は、雨が降るとどうなったのかと、くまちゃんは見に行きます。そこでは…。
おじさんのかさ (作・絵:佐野 洋子)
雨の日におじさんが出会った素敵なできごと。
りっぱなかさがぬれるのがいやで、かさをさそうとしないおじさん。
ある雨の日、子どもたちの歌をきいたおじさんは、、、

かさ (作・絵:太田 大八)
雨の中を女の子が赤いかさをさしておとうさんをむかえにいくまでに、ドラマチックで楽しいできごとに会う。
墨一色の中に赤いかさを配した絵で伝える文字なし絵本。
ずぶぬれの木曜日(作・エドワード・ゴーリー)
雨の日に主人の傘を探しに出かける犬ブルーノの物語です。
ブルーノは、傘泥棒や傘に乗って流される子どもなど、様々な出来事に遭遇しながら傘を探し続けます
かさどろぼう(作・シビル・ウェッタシンハ)
スリランカを舞台にした物語で、傘泥棒と呼ばれる老人が実は傘を修理して恵まれない人々に分け与えていたという展開。
傘は分かち合いと思いやりの象徴として描かれています。
あおいかさ (作・絵: いしい つとむ)
買ってもらったばかりの青いかさ。ぽつぽつぽつ、待っていた雨が降ってきた!
でも、風でかさが飛ばされてしまい…。
小さな女の子の感動を丁寧に描いた、青い傘と、雨と、青い空が印象的な美しい絵本。
かさじぞう(日本の昔話)
寒い冬の日に、貧しいおじいさんが自分の商品である傘を、雪をかぶった地蔵様にかぶせてあげる物語。
親切心と思いやりが報われる日本の伝統的な昔話で、傘は思いやりの象徴として描かれています。
傘をテーマとした絵本の傾向
1. 天候の変化と感情表現
傘は必然的に雨や雪と結びついており、多くの作品で天候の変化が登場人物の心情変化と重ねられています。
雨の中で傘をさして歩くことは、困難な状況の中での前進や成長を象徴することが多く見られます。
2. 保護と安全のシンボル
傘の本来の機能である「守る」という要素は、物語においては単なる雨風から身を守るという物理的な意味を超え、心理的な保護や安全を象徴することが多いです。
親子関係や友情を表現する際に用いられることが多く見られます。
3. 旅立ちと冒険のきっかけ
風に飛ばされる傘や、傘を持って出かける設定は、新しい世界への冒険や旅立ちのきっかけとして機能します。
特に子どもの読者にとって身近な傘は、冒険の入り口として想像力を刺激します。
4. 共有と思いやりの表現
一つの傘を共有するシーンは、多くの絵本で人と人とのつながりや思いやりを表現するために使われています。
特に「かさじぞう」のような昔話では、傘を譲る行為が美徳として描かれています。
5. 色彩表現のツール
傘は絵本のビジュアル面でも重要な役割を果たします。
カラフルな傘、赤い傘、青い傘など、色のコントラストが物語の展開や登場人物の個性を際立たせるために活用されています。
6. 形の変化と変身のモチーフ
傘の開閉という形状変化は、物語における変身や変化のモチーフとしても用いられます。
閉じた状態から開いて花のように広がる様子は、心の開放や成長を表現するのに適しています。
まとめ

傘をテーマとした絵本は、日常的なアイテムの中に秘められた多様な可能性と象徴性を探求しています。
雨から身を守るという単純な機能を超えて、傘は保護、冒険、分かち合い、変化など、様々な文脈で物語を豊かにする要素として機能しています。
また、子どもにとって身近な傘という存在を通して、自然現象への興味、人間関係の大切さ、冒険への憧れなど、多くのメッセージが込められています。
日本の昔話から海外の創作まで、時代や文化を超えて傘は魅力的な物語のモチーフとして今後も絵本の世界で重要な位置を占め続けるでしょう。
これをきっかけに大人も一緒に絵本を楽しんでみませんか。