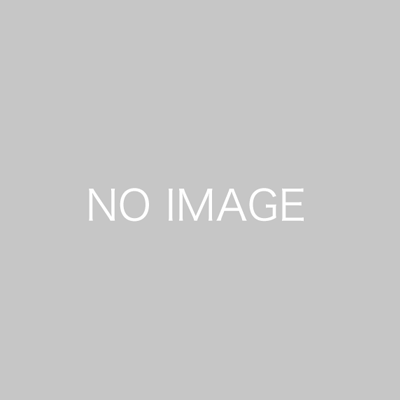日本全国にはお寺が8万弱、神社が8万以上あるそうです。どちらも生活に密接した神様仏様の社で身近な存在です。
多くの寺社は昔からその地域に存在していると思いますが、その中で傘に関係するものがあるか調べてみました。併せて傘をきれいに飾り付ける地域のイベントも紹介します。
撮りたくなる、傘に関係がある寺社や庭園、街
名古屋市北区にある「別小江神社(わけおえじんじゃ)」
写真映えのするカワイイ神社としてSNSで頻繁に投稿されているほか、全国神社人気ランキングの御朱印部門で6年連続1位を獲得したことでも話題とのこと。また色鮮やかな御朱印も非常に有名です。
伊弉諾尊(いざなみのみこと)など6神を祀っており、平安時代の「延喜式神名帳」にも記録が残っている由緒ある神社です。安産・子授けなどにご利益があります。
所在地 愛知県名古屋市北区安井4丁目14−14
別小江神社HP https://wakeoe.com/
静岡県袋井市にある「法多山 尊永寺(はったさん そんえいじ)」
静岡県袋井市にある高野山真言宗の別格本山の寺院です。
本尊は、「正観世音菩薩」「厄除観世音」であり、厄除観音として知られています。仁王門をはじめとし4つの文化財を保有しています。季節ごとに傘の飾り付けが行われています。
所在地 静岡県袋井市豊沢2777
法多山 尊永寺HP https://www.hattasan.or.jp/
群馬県桐生市にある「宝徳寺(ほうとくじ)」
ピカピカに磨きこまれた床への映り込みが有名な寺です。
春頃に和傘をテーマにした「菩提(ぼだい)樹の葉と(ハート)傘特別拝観」が開かれます。色とりどりの和傘と菩提樹の葉を模したハート形の窓が磨かれた床に映り込み、絵画のような空間を演出しています。
所在地 群馬県桐生市川内町5丁目1608
宝徳寺HP https://www.houtokuji.jp/
鳥取県 大山の大献灯 ~和傘灯り〜
古くは奈良時代の「出雲風土木」に名が記載されている歴史的にも有名な大山(寺)です。
参道に和傘を飾り付けた美しい風景を見ることができます。決まった期間の開催になりますので時期をよく確認ください。
所在地 鳥取県西伯郡大山町大山9

牡丹のお寺
京都府長岡京市今里にある「乙訓寺(おとくにでら)」
乙訓寺は京都の牡丹の名所です。春には約2000株の色とりどりの華やかな牡丹の花が咲き揃います。
所在地 京都府長岡京市今里3-14-7
https://otokunidera.jimdosite.com/
長野県伊那市にある「遠照寺(おんしょうじ)」
ぼたん寺として知られる遠照寺は、昭和57年に亡きご住職の菩提を弔うため三本の牡丹の苗を植えたのが始まりだそうで、現在では5月中旬から下旬にかけて約2,000株のぼたんを楽しむことができます。
所在地 長野県伊那市高遠町山室2010

奈良県葛城市にある「當麻寺(たいまでら)」
612年、聖徳太子の弟、麻呂子親王が創建。多くの文化財を有しており、四月下旬頃には各塔頭寺院にて牡丹の花が咲き誇ります。
所在地 葛城市當麻1263
https://www.taimadera.org/
奈良県葛城市にある「傘堂」
京都府京都市の「高台寺 傘亭(こうだいじ かさてい)」
京都市東山区下河原町、高台寺の境内にある茶室です。
高台寺は豊臣秀吉の菩提を弔うため、秀吉公の正室「北政所(きたのまんどころ・ねね様)」が慶長11年(1606)に開創したお寺。伏見城から移建されたものと伝えられます。
宝形造(ほうぎょうづくり)の屋根の内部は、丸竹を用いた化粧屋根裏が傘をひろげたように見えます。もともとは安閑窟(あんかんくつ)と呼ばれていました。
所在地 京都府京都市高台寺下河原町526
https://www.kodaiji.com/index.html

島根県松江市の「由志園(ゆうしえん)」
寺社ではありませんが、島根県松江市にある日本庭園で有名な由志園では和傘と照明を組み合わせたイルミネーションが有名です。
和傘の規則的なデザインと日本庭園のバランスが美しく、牡丹がとても有名な庭園です。
所在地 島根県松江市八束町波入1260−2
由志園HP https://www.yuushien.com/
岡山県 倉敷春宵あかり
倉敷美観地区とは岡山県倉敷市にある町並保存地区・観光地区です。
その倉敷美観地区一帯の歴史的な町並みを、影絵あかり、希莉光あかり、和傘あかり、春宵あんどんなど、日本の宵をイメージできるような、やさしくあたたかなあかりで演出されているイベントです。
岡山観光WEB https://www.okayama-kanko.jp/event/12875

鬼怒川温泉 月明かり花回廊
「鬼怒川公園ライトアップ」として和傘と明かりを使用して鬼怒川公園森のエリアを装飾します。
1年中ではなく開催期間がありますので、よく確認をしてください。
【公式】月あかり花回廊HP https://tsukiakari.kinugawa-onsen.info/
浄土宗総本山 知恩院(ちおんいん)
浄土宗の総本山。承安5年(1175)、浄土宗の開祖・法然上人が吉水の草庵を結んだ念仏発祥の地です。その後、徳川家康によって寺域が広げられました。
浄土宗の宗祖・法然が後半生を過ごし、没したゆかりの地に建てられた寺院で、現在のような大規模な伽藍が建立されたのは江戸時代以降です。
忘れ傘
知恩院に伝わる七不思議の中で最も有名なものは、「忘れ傘」と言われています。
御影堂の正面の東側から軒裏を見上げると、よく目を凝らすと、骨だけになった一本の傘の先が見えるとされています。なぜこんなに高いところに傘が忘れられているのでしょうか。これには二つの伝説があります。
一つは、江戸初期の名工・左甚五郎(ひだりじんごろう)が御影堂を建てる際に、魔除けとされた力があると信じられた傘を置いていったという説です。
日光東照宮でも有名な左甚五郎は、実在の人物か、あるいは腕利きの彫刻職人を象徴する存在として、落語や講談などでよく取り上げられる人物です。
もう一つ興味深いのが、御影堂再建以前の地に住んでいた白狐が傘を置いていったという説です。
今の御影堂は当山第三十二世の霊巖(れいがん)上人によって再建されたのですが、その落慶法要の際に大雨の中に傘を持たない童子がずぶ濡れでやってきたと言われています。
この童子は実は白狐の化身で、住処を追われたことを恨んでいましたが、霊巖上人の法話を聴くうちに心を入れ替えました。そして、霊巖上人が貸してくれた傘を軒裏に置き、「これからは知恩院を守る」という証を立てたのだそうです。霊巖上人は白狐を「濡髪童子(ぬれがみどうじ)」と名付け、山上に濡髪堂を建て、厚くお祀りしたとされています。
この濡髪堂は、その名前の響きからか、今では縁結びを含め、さまざまな願い事をする若い人たちの参詣が絶えないと言われています。
所在地 京都府京都市東山区林下町400
知恩院HP https://www.chion-in.or.jp/en/highlight/wonders.php
山口県萩市の 「松陰神社(しょういんじんじゃ)」
松陰没後の1890年、松下村塾を改修する際に、松陰の御霊を祀る祠を建てたことからはしまった、吉田松陰ゆかりの神社です
本社は、1907年には松下塾の門下生だった伊藤博文らの働きで創建。現社殿は1955年に竣功。御神体には、松陰が愛用していた赤間硯と遺言が納められています。
「松陰神社」には、「傘が開く」と「運が開く」をかけた、女子に大人気のおみくじ「傘みくじ」があります。
所在地 山口県萩市椿東1537番地
松陰神社HP https://showin-jinja.or.jp/

傘みくじは、他にも東京都荒川区にある素戔雄神社、奈良の當間寺、徳島では津峯神社と十楽寺(四国八十八ヶ所第7番札所)、香川県では一宮寺(四国八十八ヶ所第83番札所)などいろいろなところにあります。
山形県 酒田市の 「傘福」
まとめ
神社やお寺、庭園がいろいろな形で傘と関わっていることがわかりました。
傘を参拝者に向けてアピールすることに活用したり、おみくじや奉納物として使われているなどいずれも写真映えしそうなものばかりでした。
ここに紹介した以外にも傘と関連した寺社はまだまだあると思いますので、ぜひお知らせください。
また、気になったところがありましたら、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。